日本の伝統文化や技術を維持・継続するため
弊社は昭和50年に設立されました。
日本の伝統文化を守るため、古来の伝統的な手法を大切にし、
日々の業務に取り組んでいます。
施工内容
珪藻壁

プランクトンの死骸が堆積して形成された珪藻土は、海底で採取される自然素材で、保湿性や保温性に優れ、調湿性能の高い土壁材の一種です。この素材は壁材としてだけでなく、私たちの生活のさまざまな場面で利用されています。具体例としては、魚や肉を焼くための七輪、断熱素材としてのレンガ、さらにはビール工場で使用されるろ過フィルターなどがあります。
珪藻土は多孔質でミクロの穴が多数存在し、湿気を吸収しても蒸発によって水分を効率よく放出する特性を持っています。このため、カビが発生しにくく、消臭効果も期待できます。また、高い抗酸化作用を備えているため、室内の空気を健康的な状態にろ過する役割も果たす、非常に優れた壁材です。
漆喰壁
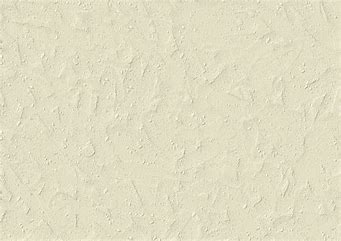
水酸化カルシウムを主成分とする消石灰を用いた土壁の素材は「漆喰」と呼ばれます。具体的な配合としては、消石灰に砂、ノリ、紙スサ、麻スサを混ぜ合わせたものです。この漆喰は土壁の上塗りに使用され、劣化を防ぐ役割を果たします。また、調湿性能や殺菌機能を持つため、左官素材の中でも特に高い耐久性が期待されます。
漆喰は壁材としてだけでなく、屋根にも使用され、棟部分の補強にも役立っています。湿気に強く、ひび割れしにくいという特徴を持つ一方で、その性能を十分に発揮させるためには、熟練した左官職人の技術が求められる素材でもあります。
屋根の漆喰補修工事

屋根瓦のつなぎ目には漆喰が使用されており、腐食に強く耐久性の高い素材ですが、雨風にさらされる環境では剥がれることがあります。漆喰が剥がれると瓦がずれて破損し、雨水が侵入する原因となるため、破損箇所を発見した場合は早急な修理が必要です。雨水が建物内に侵入すると、建物全体の劣化につながる恐れがあるため、小さな破損でも放置せず、適切に対応することが重要です。
漆喰の補修作業では、まず剥がれた漆喰を取り除き、その後新しい漆喰を詰め直して瓦を正しく設置します。適切な補修を行うことで、屋根の耐久性を保つことができます。
施工実績
岩崎弥太郎生家

「東洋の海上王」と称され、三菱財閥の基盤を築いた岩崎彌太郎の生家は、安芸市内から北へ約3kmの井ノ口に位置しています。この生家は修復保存されており、1795年頃に彌太郎の曽祖父である弥次衛門が郷士の株を売却して建てたわら葺きの平屋建築です。また、生家の西側と後方にある土蔵の鬼瓦には、岩崎家の家紋である「三階菱」が刻まれており、これが現在の三菱マークの原型とされています。
年に一度、修繕工事を実施させていただいております。
土居廓中・武家屋敷

土居廓中には、現在も武家屋敷が残り、昔ながらの風情を感じることができます。竹やうばめ樫の生垣に囲まれた武家屋敷が立ち並び、静かに当時の趣を伝えています。その中で唯一一般公開されている野村家住宅は、現存する建物の中で最も古く、天保年間(1830年頃)に建てられたと推定されています。この住宅には「武者隠し」と呼ばれる高さ約3尺(約90cm)の壁があり、玄関脇の平次門をくぐると小さな庭が広がり、その先には菜園が設けられています。
土佐藩家老である五藤氏が安芸城跡に入った後、廓中の町並みが整備され、それぞれの役職に応じた屋敷が与えられました。こうして現在に残る廓中の武家屋敷が形成されたと言われています。
藩政時代、この区域には農民や商人は住むことが許されず、明治時代以降も廓中に入る際には頬被りや鉢巻を外すことが求められたと伝えられています。



